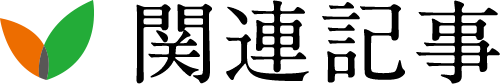映画監督 溝渕雅幸さん 「家族にも言えない話」を聞いて


戦争について話してくれた父母について語る溝渕雅幸さん(今泉慶太撮影)
戦争の影があった子ども時代
都市銀行に勤めていた父は転勤が多く、私は福岡で生まれ、大阪・奈良で育ちました。父は忙しく、一緒にだんらんした記憶は少ないです。
それでも私が小学校高学年になるころかな。奈良に移って父の忙しさも少し落ち着き、たまに家で夕食を共にすると、戦争の話をするようになりました。父は昭和5(1930)年生まれ。勤労動員で高松の飛行場の整備をしたと聞きました。米軍の戦闘機は四国沖の空母から発艦し、本州の呉などを攻撃したり、爆撃機を護衛したりする。その帰りに、四国で面白半分に人だろうと小舟だろうと、機銃掃射する。そんなものも見たそうです。
母も疎開先の宮崎で軍需工場に動員された。たまたま大阪に戻っていた時、京橋空襲に遭遇。火の間を逃げ回り、防空壕(ごう)で過ごしたことを話してくれました。
私が過ごした昭和40年代初頭の大阪もまだ、戦争の影がありました。ヤミ市の雰囲気が残り、兵器工場の鉄くずを拾う人もいました。梅田の歩道橋では傷痍(しょうい)軍人が募金を呼び掛けている。小銭を入れると、思いも寄らない大きな声で「おありがとうございます!」。その声は今も耳の奥に残っています。
人生の「織り直し」を支える
おかげで戦争の話を聞く耳は開いていました。新聞社を辞め、番組・映像制作の仕事に携わった時、戦争体験を残したいと思いました。南方の激戦地の話など、存命の方を探して話を聞きました。
生々しい話です。加害者としての体験も含まれます。ある人の話を聞いた後、その息子さんが駅まで車で送ってくれたことがありました。隣の部屋でふすま越しに聞いていたという息子さんが言いました。「父から一言も聞いたことがない話でした」と。家族にも言えない話だったのです。しかし、寿命を考えれば今語らねばと、苦悩の末に話してくれたのです。
それは、生きている間に自分の人生を整理するプロセスだと感じます。つらいこと、苦しいこと、失ったもの、取り返しの付かない過ち。その事実は変えられません。でも、それを「織り直す」ことで、自分の人生を意味あるものにすることはできるのだと。
「みとり」をテーマに映画を撮っています。私もみとりとは、息を引き取る瞬間に立ち会うことだと考えていました。でも、話すうちに見えてきました。その人の言葉、心の声に耳を傾け、その織り直しを支えるところからみとりは始まるのだと。戦争体験とみとり。無意識に私が追っていた2つのテーマは、実はつながっていたのですね。
父母は今年で88歳と89歳です。久しぶりに、話を聞きたくなりました。
みぞぶち・まさゆき
1962年福岡県生まれ。大阪日日新聞社の記者を経て、90年からディレクターとして教育映画、テレビ番組など、多数の映像作品を演出した。2013年に映画「いのちがいちばん輝く日~あるホスピス病棟の40日~」で劇場用映画監督としてデビュー。「死の瞬間」もカメラに収めた。18年、2作目の「四万十~いのちの仕舞い~」を公開。
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい