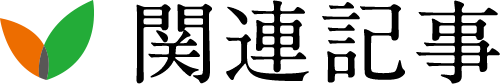演出家 宮本亞門さん 悩んでいた時、空港でおやじに手渡された小さな紙


家族との関わりについて話す演出家の宮本亞門さん(佐藤哲也撮影)
94歳のおやじに学ぶ 生きることの壮絶さ
94歳のおやじは認知症が少し進み、体も動かなくなってきてますが「生きるぞ、生きるぞ」って自分に言い聞かせてます。旅行が好きで、この前も僕が運転して軽井沢に行きました。向こうで姉たちを待たせ、サプライズで会わせたり。おやじは「生きていると何が起こるか分からないね」と喜んでました。
何回も手術したりして、僕はおやじに生きることの壮絶さを教わっている。老いていくことで何かを学んでいく。それはマイナスではなく、心がずっと変わっていける。老いは壮絶で醜悪かもしれないけど、限りなく美しい。
おやじはおふくろと駆け落ちをして、東京の新橋演舞場の前で2人で喫茶店を始めました。母を愛し、一緒に生きようと決めたのですが、僕が21歳の時におふくろが亡くなった。おやじは「生きる価値があるのか」と、ぼろぼろになっちゃったけど、店だけは休まなかった。母が残したものをとにかく受け継ぐんだと思ったのでしょう。
ミュージカル「太平洋序曲」の打ち合わせで米国に行くとき、おやじが成田空港に送ってくれた。僕がいろいろ悩んで弱音を吐いていると、別れ際に小さな紙をくれた。機内で広げたら「人生悩んでいるには短すぎる」と。粋なことやるなあって思ったけど、その言葉がすごく染みた。
がんになって思い出した、おふくろの言葉
僕は演出家になる前、ミュージカルなどの舞台に出ていました。ダンサーだったおふくろが亡くなったのは僕が出る舞台の初日の朝。巨大なバトンを渡された思いでした。本来おふくろが座るはずだった客席に花束を置いたとき、「あー今度は上から見てるんだ」とスイッチが変わった。
僕が生まれたときに輸血肝炎になり、何回も死の宣告を受けていたんです。おふくろには演出家になった自分の舞台を見てほしかった。「お母さん、見てね」とポケットにおふくろの写真を忍ばせているんです。おやじがブロードウェーに来てくれた時は客席で手をつないで舞台を見て、「きっと見てるよね」と2人で泣いたこともありました。
おふくろは家族旅行の旅先の朝、「今日も生きてる、とにかく今日も生きてる」と、いつも太陽を拝んでいた。「同じように見える景色でも、毎日全部違うのよ。よく見なさい」と。生きることの一瞬たりとも無駄にしない。僕は昨年前立腺がんを患って、その言葉を思い出します。
父と母の人生を合わせて自分なりに感じたことを伝えるために、演劇という道具を使わせていただいているのが僕なんです。こんなにいろんな人が生きて。だからいいよね、おもしろいよね。人間っていとおしいよね、と。
宮本亞門(みやもと・あもん)
1958年、東京都生まれ。2004年に東洋人初の演出家として米ブロードウェーで「太平洋序曲」を上演するなど、国内外で広く活躍。自らのがんとの向き合いなどをまとめた著作「上を向いて生きる」を今年10月に出版。がんから復帰し、「亜門」を「亞門」と改名した。舞台「チョコレートドーナツ」を年内は東京・PARCO劇場で、来年1月29~31日に愛知県東海市芸術劇場で上演予定。
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい