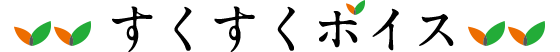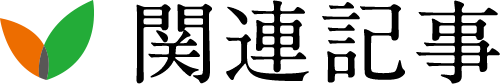ライター 尹雄大さん 40歳を過ぎて気づいた、自分の中の「母への怒り」と「父の声」

ライターの尹雄大さん(坂本亜由理撮影)

17歳で母が亡くなり「裏切られた」
母は僕が生まれて間もなく、膠原(こうげん)病になり、僕が17歳のとき亡くなりました。4歳のころ、入院先から帰宅した母の顔が薬の影響でパンパンに膨らんでいるのを見て、「全然知らない人がそこにいる」と感じたのが、母の病を認識した最初でした。
アルバムを見返すと、その日を境に僕の表情は変わっています。母は死ぬんだな、と無自覚に悟ったのでしょう。そこからは、母に迷惑をかけちゃいけない、いい子でいなければ母は死んでしまう、と強く思い込んでいました。僕、一度もおねしょをしたことがないんです。
母が亡くなった後、一切の感情がフラットになりました。自分では冷静なんだと思っていたけれど「そうじゃない、あれは怒っていたんだ」と気づいたのは、40歳を超えてからです。いい子にしていたのに母に見捨てられた、裏切られたという怒りです。
そうした母との関係性はその後、女性とのつながりに映し出されました。自分を理解してくれる存在であると同時に自分を見捨てるだろう、だから期待してはいけないと。感情を出さず、親密になりかけるとよそよそしくなるといった言動は、関係を長続きさせられませんでした。
「男なら」抑圧的だった父、実は…
母への「怒り」に気づくとともに、「男なら頑張らなくてはいけない」と自分に言い聞かせてきた声が、自分のものではなく父の声であることにも気づきました。高度経済成長の中、父は事業を大きくして社会的地位や尊敬を得ることが重要だという人でした。家の中ではとにかくいつも怒っていて、母や僕と兄にも抑圧的でした。
6年ほど前、父とじっくり話して分かったことは、父の怒りは感情ではなく、彼の受けた傷の発露だということでした。「貧しく、人間の底辺の暮らし」と振り返る子ども時代。弱い立場に置かれ無力な大人を見ても、幼い父にはどうすることもできなかった。弱い人を見ると怒りが募るというのはそこに原因があるのではないかと感じました。
だから父も仕方なかった、という単純な話ではなく、父には父の必然性があり、その父の元に育った僕にも、何らかの影響が及ぶのは仕方のないことだったんだと思えました。
人とうまく話せないとか、感情表現ができないとか、長い間社会とのつながりがぎくしゃくしていた僕ですが、両親との関係性を整理することで、心のうちを話し、分かり合える人間関係を生きられるようになりました。親から受けた傷があるのは確かだし、葛藤は完全になくならない。でも、どうにもならないことをどうにもならないままに生きるしかないということもある。それが、自分の人生を生きる責任だと思っています。
尹雄大(ゆん・うんで)
1970年、神戸市生まれ。テレビ番組制作会社や出版社などを経てライターに。インタビュー原稿やルポルタージュを手がける。政財界人やアスリート、アーティストなど約1000人への取材や自身の武術体験を基にした身体論などが注目されている。著書に「さよなら、男社会」(亜紀書房)「モヤモヤの正体」(ミシマ社)など。
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい