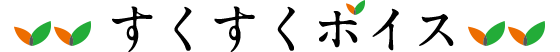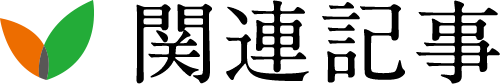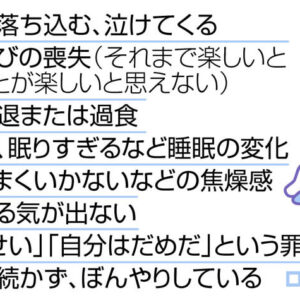「大ピンチずかん」鈴木のりたけさんインタビュー 子どもたちに伝えたい「物事に正解なんてない。面白がれば世界は広がる」

アトリエでインタビューに応じた鈴木のりたけさん(市川和宏撮影)
少年時代は怒られることもいっぱい
―大ピンチずかんは、息子さんの姿がヒントになって生まれたそうですね。
表紙にあるように、牛乳をこぼした次男がフリーズしちゃったんですよ。親からしたら「おいおい、早く拭きなさいよ」と言いたくなるんだけど、子どもにとってはすごいショックなことだな、とも思うわけです。

「大ピンチずかん」(小学館)
人間って、先生に教えられて成長するだけじゃなくて、そんな経験を重ねることで階段を一段ずつ上っていく。絵本ではそれを「あるある」って笑って終わらせるのではなく、どう受け止めるかを考えることで、話を広げていきました。
―ご自身はどんな少年だったのでしょうか。
浜松市の実家は当時、うっそうとした森や谷がそばにあるところでした。崖で秘密基地をつくったり、爆竹を投げ合ったり。怒られるようなこともいっぱいしました。寒いから友達とたき火をしようとして、壁が真っ黒になっちゃったことも。1回、先生に悪さを見つかったことがあったんですけど、友達がかたくなにかばってくれた。あのときのいたたまれなさは、忘れられない…。

日記の読み上げで「笑わせる快感」
―絵の話が出てくる気配が全然ありません。
少年ジャンプの全盛期。鳥山明さんの絵の模写なんかはしてましたよ。自分がエースで4番という野球漫画を描いたこともあった。相手はなぜかロボット軍団という設定でした。でも誰かに読ませるわけではなく、たくさん時間をとって描くほどでもなかった。
むしろ、よく覚えているのは日記のこと。中学1年のとき、生徒が提出する日記で面白いやつを担任が読み上げる時間があって。選ばれるとすごく、うれしい。「おいオザワ、ちゃんと聞いてるか」って担任のせりふまで書いておいたりして、みんなが笑ってくれるのが快感で。毎日、一生懸命、考えてました。
―好きだったのは「人を楽しませる」ことだったんですね。
喜んでくれると、自分も楽しくなる。今は絵本作家だから、「絵を描くことが幸せです」って感じに思われがちですが、そうじゃないんです。絵は手段であって、その先にあるものに価値を見いだしていたい。

高校の学園祭で「タイツマン」!?
―絵本作家を目指していたわけではなかった。
10代の頃、なりたかったのは弁護士でした。口が達者だったんで「人のために使いなさい」と先生に言われたのがきっかけで。でも、判例に従って考えるようなやり方は向いていないと気づいてやめました。「前例踏襲」が苦手なんです。効率的で一番の近道だけど。新しいことに挑戦する方が楽しい。
例えば高校の学園祭。模擬店とか毎年、同じようなものをやるじゃないですか。3年のときは全然違うことをやろう、ってできたのが「タイツマン」。教室で授業の様子を見せるんだけど、みんな白い全身タイツを着ている。「タイツは一日にしてならず」とか黒板に書いて、変な生き物がまじめに学んでいるという。
新しいことをやるって、面倒なこともたくさん起きる。嫌がるクラスメートを説得したり、事前にネタバレしないようにニセの企画書を出したり。でも、そのドキドキ感が楽しい。

―最初に選んだ仕事がJR東海というのは、意外な感じがします。
大学のときはマスコミ志望だったんですけど、JRは当時、関連事業を幅広く手がけていこうという動きがあった。面接で「もっとこんなこともできますよ」と大風呂敷を広げたら、面白がってくれたんです。研修で新幹線の運転もして、最終的には新規事業の担当部署に配属されたんですが結局、1年9カ月で、すぱっと辞めました。
文章を書くのが好きだし、いろいろ調べて知らないことに出会っていく、ということをやりたくなって。取材をしてイラストを描いて仮想の雑誌なんかをつくるというゲリラ的な活動を始めました。ただ、それを持って雑誌関係を回っても未経験者だから採用されない。貯金が尽きてきてやばい、と思ったときに広告制作プロダクションのデザイナーになれました。
JR、デザイナー… 遠回りした末に
―どんな仕事を。
新商品のビールの広告、みたいなことです。「デザイン、イラストとはなんぞや」ということを、そこで学びました。本を大量に読んで、家に帰っても自分で描きたい絵を描いていた。シニカルな社会風刺のようなものだったんですが、一枚でテーマや思いを伝えるのは大変だから、連作にしてみた。もっと分かりやすくするために、せりふをつけてたら「なんか絵本っぽいぞ」って。それで出版社に応募したら、賞がもらえたんです。

―だいぶ遠回りしました。
その分、今までにない絵本を作れるかもしれない、という考えもありました。デザイナーを8年やって、情報をまとめて分かりやすく提示する技術はつちかっていた。それでまた、会社を飛び出しました。「事務所を継ぐか?」とまで言われていたんですけど。
絵本のこともあらためて勉強しました。ただ、崖で遊んでいたような子どもでしたから、どんな作品が好きだったか、あまり思い出せない。それでも、おふくろが自作の絵本を読み聞かせてくれたことや、かこさとしさんの科学の絵本シリーズを食い入るように読んだ記憶はあった。かこさんの本は、世の中の仕組みが全部つまびらかにされているようで「世界のことが分かっちゃった」と感じてぶるぶる震えるほどでした。再読して「こんな本を作りたい」と思いました。
面白いかどうかは、自分の価値観次第
―紆余曲折も楽しんできたんですね。
いやいや、大変でしたよ。本当に戻りたくはない。今になってみれば、いい経験をしてきたと思いますが。世の中、挑戦してもうまくいくことばかりじゃない。開いた扉の先にあったものが、しょぼいことだってよくある。でも「しょぼささん、来てくれてありがとう」と愛(め)でたい。
面白いかどうかは、自分の価値観次第。石ころ一つだって、輝いて見えることがある。面白がると、世界が広がる。そのほうが幸せです。絶対。

「大ピンチずかん2」(小学館)
―大ピンチずかんも、見方を変えて俯瞰することで、ピンチを楽しむという仕掛けになっていますね。
そういう面白さにぜひ、子どもたちも気づいてほしい。面倒なことも増えるかもしれないけれど、衝突し合いながら「あるよね、そういうことも」って生きていける。必要なのは「物事に正解なんてない」という自覚です。私たちはどうしても「答え」というものがあって、それを早く見つけないといけないという教育を受けてきていますから。でも、そこに行き着かないとだめだというのは、まったくもって違う。その人なりの正解があって、人と違うことや、道が生まれることに価値があるはずです。

インタビューを終えて
絵本のCMなんてあるのか。テレビで見たときは驚いた。そんな時の人は、記者と同郷の「先輩」でもある。何を見て、どう育ってきたのか、とても気になっていた。
アトリエで、面と向かってする会話も面白い人だった。取材の録音には、記者自身の笑い声がいやになるほど入っていた。そりゃあ、タイツマンなんて言葉が出てくるとは思わないでしょう。
感じたのは、人を楽しませるだけではなく、何でも楽しむことができる達人だということ。「やりたいことは尽きない。わくわくしてますよ」。少年のような「わくわく」という言葉が、とても似合っていた。

鈴木のりたけ
本名・鈴木典丈。1975年、浜松市生まれ。浜松北高、一橋大社会学部卒。JR東海、広告制作プロダクションを経て、2008年に「ケチャップマン」(2015年に復刊、ブロンズ新社)で絵本作家としてデビューした。2022年の「大ピンチずかん」(小学館)は、第6回未来屋えほん大賞など、絵本関連の賞で8冠を達成。第2作を2023年に刊行した。美容師や新幹線運転士といった、さまざまな職場を取材して事細かく再現した絵本「しごとば」シリーズ(ブロンズ新社)や、「ぼくのおふろ」(PHP研究所)など著書多数。近著は「オバケや」(文・富安陽子さん、小学館)。千葉県在住、2男1女の父。子育ての信条は「待つこと」だという。
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい