母と子のありようを描く「星を掬う」著者・町田そのこさんインタビュー そのしつけ、子どものため、それとも親のため?

※以下のインタビューは本の詳細な内容も含みます。未読の方はご注意ください。
「星を掬う」のあらすじ
人生を諦めている29歳の芳野千鶴は、ある出来事がきっかけで22年前に自分を捨てた母・聖子と再会する。元夫のDVから逃げるため、母の住む「さざめきハイツ」で同居を始めた千鶴。聖子を「ママ」と呼ぶ恵真(えま)、理想の母のように優しい彩子(あやこ)、10代で妊娠した彩子の娘・美保との奇妙な共同生活の中で、新しい答えを見いだしていく。

虐待する側の事情 見つめる娘の視点
―ご無沙汰しています。遅ればせながら、本屋大賞、受賞おめでとうございます。
「ありがとうございます。もう夢みたいで。いろいろな人に祝福されて、本屋大賞という存在が、さらに大きく、重たくなって。もう浮ついたものは書けないと気を引き締めました」
―前作はテレビで見た子どもの虐待のニュースがきっかけでした。今作を書こうと思ったきっかけは?
「52ヘルツのクジラたち(以下52ヘルツ)を書き上げたとき、続編は書かないつもりでした。でも、もし書くなら今度は前作とは逆の、虐待する側の視点、世の中から批判されるようなことをした母親の、そうせざるを得なかった事情と、それを見つめる娘の視線かなと思っていました。時がたつにつれ、その思いが強くなっていったんです」
5人の同居女性 いろいろな母子の姿
―「母と子のありよう」というのは難しいテーマです。
「そうですね。特に女同士、母と娘は難しいですよね。私、母と娘には相性があると思うんです。血のつながりがなくても母子のような関係になれることがあるし、肉親だからこそ傷つくこともある。組み合わせや愛し方、考え方一つで、母子関係は変わる。だから、本の中で5人の女性を同居させ、いろいろな母子の姿を描いたんです」
―今、「親ガチャ」という言葉がありますね。子どもにとって親はカプセル式玩具のように自分で選べないという否定的な意味で使われますが、作中にも、17歳の美保さんが自分の不幸はあなたの娘に産まれたからだと彩子さんを責めるシーンがあります。
「書いているときは、まだ親ガチャという言葉は出てきていなかったのですが、視点は同じだったので、驚きました。でも、私も親の束縛が強かったので、20代のころに聞いていたら、私も同じようにその言葉を使っていたかもしれない。そう思うと一概に責められないと思います」
「親ガチャ」 自分の人生の責任とは
―なぜ、親ガチャという言葉が広まったと思いますか?
「『この人のせいだ』って、誰かに責任をなすりつけている間は楽なんです。自分自身は傷つかなくていいわけですから。でも、自分の人生に対する責任を自分で捨ててはいけない。自分の人生、自分で選択をして決めていくんです。そういう思いでこの作品を書きました」

―子どもが自分で自分のことを決める、子どもに自分のことを決めさせる教育は正しいのでしょうが、いざやるとなると、難しいです。
「うちも娘が中学3年生なので、行きたい高校を聞いていると、つい口出ししたくなるんです。でも、後で『ママが選んだから、私失敗しました』って言われたらと思うと強くも言えない。それでも、親は娘より物事を見ている分、私の意見にいずれ娘が感謝する日も来るんじゃないかとも思って…。そこにまた、私の母が『あんたのときはこうだった』とかいうから、もう収拾が付かなくなって(笑)。最終的には娘が自分で決めました」
「私なんて」から一歩踏み出す瞬間
―作中、しつけとして子どもに自分の考えを押しつけ、自分そっくりに育てようとする母親が出てきます。
「親は子どもを自分と同じ人生にしたり、自分が知っているところに入れておけば大丈夫だって思うんです。それも一種の親の愛なんでしょうけど、子どもは自分ではない枠に押さえ込まれるのがしんどかったりする。親の愛と子どもが受け取るものって全然違うことを考えないといけないとは思いますね」
―親の行きすぎた愛はエゴになる?
「誰でも、自分の子には失敗してほしくないと思うんです。でも、それは束縛であり、強制なんですよね。私、最初の子が生まれたときに、『この子の人生にある全ての障害を私が拾っていきたい』って思ったんですよ。でも、今になって、『私が拾った障害はこの子が乗り越えなければいけない、つまずかなければいけない障害だったのかも』と思うときがあって。親のありようって難しいなって考えます」
―なるほど。それでこの作品を書いたんですね?
「主人公の千鶴は自分の不幸を人のせい、親のせいにして生きています。今回は、人に自分の人生の責任とか決定権とか、そういうのを預けっぱなしにして、『私なんて』って自分をおとしめてきた女性が自分の意志で人生の一歩を踏み出す瞬間が書きたかったんです」
祖母のオムツ なぜ私はできないの
―もう一つの大きなテーマは親の介護です。主人公は母の認知症介護に直面するわけですが、町田さんは介護の経験はあったのですか?
「両親は健康なんですけど、祖母が認知症で。私、おばあちゃん子だったんですけど、寝たきりになった祖母のお見舞いにいったとき、ホームの職員さんから『オムツを替えるので席を外してもらえますか』と言われたことがあったんです。そのとき、いとこは介護の仕事をしているので『手伝います』って残ったのに、私は真っ先に部屋から出てしまった。こんなに育ててもらったのに、祖母のオムツを替えることを拒否した自分がショックで…」

―その後も悩んだのですか?
「なんで私はできないのって思いながら、でも、泣きながら私がオムツを替えて祖母は喜ぶのだろうか。それが祖母を傷つけるのではないか。それがすごくしこりになっているんです」
―作中の弄便(ろうべん)のシーンは衝撃的でした。
「認知症の人は、便をいじってしまうことがあるんです。それが弄便。私も知ったときはショックでした」
―認知症を患っている聖子さんですが、22年前、なぜ娘を捨てたのかが、物語最大の焦点になりますね。
「答えは読んでいただいて…(笑)。でも、実は最初の設定では、聖子さんは娘の千鶴と同じようにうじうじ悩む性格だったんですよ。でも、子どもを捨ててまで自分の人生をもぎ取った人が、後悔して生きていてほしくない、胸を張っていてほしいと、今の形に改稿したんです」
「星を掬う」タイトルに込めた意味
―今回の作品は随分書き直したと聞きました。どこを変えたのですか?
「ほぼ全部です。残したのは、最初と終わりのちょっとしたところくらい。最初に書き上げたものとは、千鶴の母・聖子さんは名前も違いますし、性格も正反対の設定で、書き直しすぎて、全く別物になりました。何度も一緒に考えていただいた担当さんに感謝しています」
―どうして書き直しを。
「52ヘルツに似たものになったというか、あれにミステリーとかサスペンスの要素を加えただけになってしまって。私が書きたかった母と娘のありようはこれじゃない、そう思って書き換えました。立派な賞をいただいたので、自分が納得するものを出したかったんです」
―星を掬うというタイトルが美しいです。この言葉は物語の核心にも迫ります。どうやって思い付いたのですか。
「祖母がそうだったんですが、認知症の人って急に誰かと会話を始めたりするんです。お兄さんを思い浮かべて『あの時、兄ちゃん、こう言っていたでしょ』とか。あ、今、祖母は記憶がごっちゃになっていて、見ている世界がすっと口から出ているんだろうなって。この人が今見ている世界、掬い上げた世界って不思議だなって考えたんですよね」
家族との関係 振り返るきっかけに
―母子の次はどのような作品を書いていきたいですか?
「先日、お会いした辻村深月さんはホラーを書かれたと聞いたので、私もいろいろやりたいって思っています。ティーンの恋愛も書いてみたいし、40代の今の私と同世代の主人公が、幼なじみと再会したときにお互いの人生を振り返るみたいなものも書いてみたいです」
―最後に町田さんと同じ子育て世代の読者の方にひと言。
「そうですね。この本を読んで、自分のお母さまでも、お子さんでも、家族の関わり合い方とか、思いの伝え方を一度振り返るきっかけになればと思います。私はこの子を束縛していないだろうか、自分の夢を押しつけていないだろうか、そして、この子が自分に遠慮していないか、言いたいことを言えているかどうか、とか。そういう母と子のありようを見直すきっかけになったのなら、うれしいですね」
町田そのこ
1980年生まれ。福岡県在住。2017年、「女による女のためのR-18文学賞」大賞受賞作を含む「夜空に泳ぐチョコレートグラミー」(新潮社)でデビュー。他の著作に「ぎょらん」「コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―」(新潮社)、「うつくしが丘の不幸の家」(東京創元社)がある。2021年、「52ヘルツのクジラたち」で全国の書店員が選ぶ「本屋大賞」を受賞した。
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい

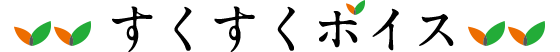
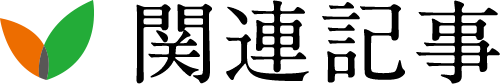








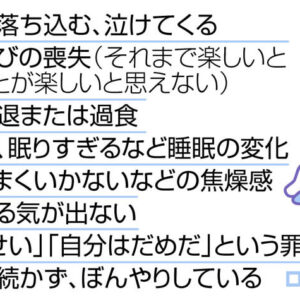
王様のブランチでコメンテーターが泣きながらこの本の紹介をしていたので買って読みました。そして読んでからこのインタビューを見つけて、あ、あの場面はそういう意図だったのか、あのシーンは町田さん自身の体験だったのかと興味深く読むことができました。自分の不幸を他人のせいにして、私なんてって自分をおとしめてきた女性が自分の意志で人生の一歩を踏み出す瞬間が書きたかったってところが素敵だと思いました。町田さんの思いが伝わる良い記事でした。
町田さんの思い、すごい分かる。こどもの前の障害を全て取り除きたいってところや、うちも祖母の介護で同じような思いをしたから。この本は読んでなかったけど、すごく読みたくなった。