ドッジボールがうまくなりたい人、集まれ!「よける」「なげる」「とる」日本代表選手が教える3つのコツ


「日本代表選手が教えるドッジボール教室」に参加した子どもたち(取材協力=コナミスポーツ)
合言葉は「思いやり」
今回のドッジボール教室は3月23日、豊島区のスポーツ振興施策推進事業の一環として、南長崎スポーツセンターで行われました。講師は2018年度日本代表の森口真衣さん(22)と2022年度日本代表の小池吉崇選手(40)です。森口さんが「こんにちは~。今日はよろしくお願いします。私のことは、マイちゃんって呼んでくださいね~」といえば、小池さんも「今日はみんなで楽しみましょう!」。元気のよいあいさつに、子どもたちも思わず笑顔になりました。

子どもたちに自己紹介する森口真衣さん(右)と小池吉崇さん(中)
自己紹介が終わると準備運動です。集まった20人(小学生低学年11人、幼稚園年長9人)が広がって、体を動かします。ここで、森口さんが子どもたちにひと言。
「今日は一つだけ合言葉を覚えていってください。『ドッジボールは思いやり!』。覚えましたか~。ドッジボールは一人で頑張るスポーツではありません。みんなで楽しむスポーツです。いろいろな人と一緒にチームで遊ぶスポーツだということを忘れないでください」
子どもたちがこの言葉の意味をわかるのは、もう少し後のこと。今は先に進みましょう。
1 ドッジは「よける」という意味
それでは、早速、教室の様子を見ていきます。最初に2人が教えたのが、球のよけ方です。「ドッジボールのドッジってどういう意味かわかる人~」と森口さん。子どもが手を挙げて、「逃げる!」と答えると、「そう! すごい! よく知ってるね~。ドッジボールは名前の通り、投げること、取ることが苦手でも、最後まで逃げられたら勝ちというスポーツです。だから、まずはよけ方からやっていきましょう」
よけ方は、大きく分けて3種類あります。「最初はボールが下に来たときです。下に来たボールをとるのは難しいので、ジャンプしてよけます。このとき気をつけるのが足。閉じたままだと当たってしまうので、足を広げてジャンプしてね~」
続いて、上に来たボールへの対処。「上に来たボールはしゃがみます。でも、すぐにこっち(外野)からボールが来るよね。なので、すぐに起き上がれるように、しゃがむときは片足のひざをつくようにしゃがむこと」

横に来たボールを想定して体を動かす子どもたち
「最後は体の横に来たボールです。横にきたボールは無理にとると当たってしまうので、よけます。そのとき、手も足も思いっきり、横に動くと当たりにくいです! そうそう、その調子!」
森口さんが「下!」と言ったらジャンプ、「上!」と言ったらしゃがむ。子どもたちは「キャーキャー」言いながらも、夢中で練習していました。
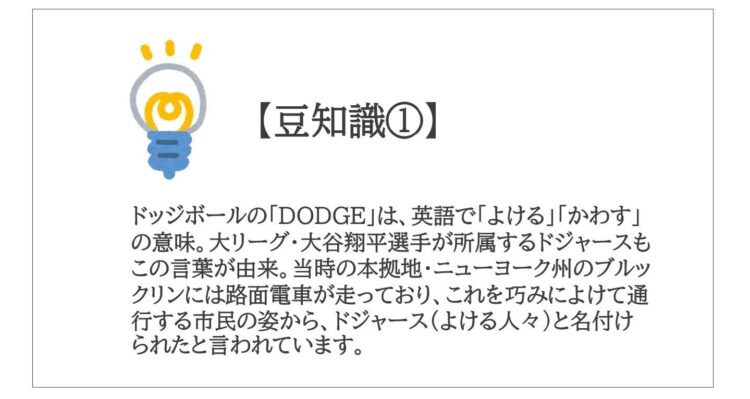
2 投げるコツは「体重移動」
次は、投げることに挑戦です。最初に森口さんと小池さんがそれぞれ実演します。大人の速いボールを見て、「わぁー」「速っ!」と大騒ぎする子どもたち。森口さんは「私は身長153センチくらいですが、最速で92キロ出ます。みんなとそれほど身長は変わらないと思うので、みんなも速い球を投げられるようになります」
速く投げるコツはどこにあるのでしょう? ヒントは体重移動にありました。
「まず、体は横を向き、顔を投げる方へ向けます。そして、1で、後ろの方の足に体重を乗せてください。十分に体重が乗ったら、2で、前の足に体重を乗せまーす。はい、1、2、1、2…」


後ろの足に体重を乗せてから、前の足に踏み出すと速い球が投げられる
子どもの吸収力ってすごいですね。何度か練習すると、だんだんと強い球が投げられるようになってきました。頃合いを見て、森口さんがこう告げます。「コントロールよく投げるには、目と手と足を同じ方向に向けること~」。子どもたちは、お友達やお母さん、お父さんに向かって、いつまでもボールを投げ続けていました。
3 「キャッチ」はおなかの真ん中で
最後はボールの受け方です。ピニャさんの愛称で親しまれる小池さんが実演します。
「まずは、足を肩幅くらいに開いてください。開きすぎると動きにくく、閉じたままだと後ろに倒れてしまいます」
続いて「お尻を下げて、低い姿勢に」。あとは「おなかの真ん中でキャッチします。キャッチした後は、コロコロしないように腕で抱きかかえます。そのとき、自分の鼻がボールにつくくらい抱きかかえると落とさないのでいいですよ!」

ボールをとる見本を見せる小池さん(左)
そして最後は、待ちに待った試合です。トマトチーム、バナナチームに分かれて、保護者の大人チームと対戦したり、子どもたち同士で対戦したり。みんな真剣そのものでした。ここで森口さんが子どもたちに話しかけます。「みんな~、試合で一度も投げていないよって子がいたら、次はその人が投げられるようにボールを渡してください。全員が投げられるようにね~」

見事なフォームで投げる子ども。練習を積んでみんな格段にうまくなりました
ここで子どもたちが、「思いやりってこと?」。「そう! みんな、えらいね。もう覚えたね。ドッジボールはうまい人でも、運動が苦手な子でも一緒にコートで戦うスポーツ。だから、それを忘れないでね」と森口さん。実はドッジボールは上級者ほど、初心者をカバーしてプレーするのだそうです。運動のコツと同時に心得も伝授されて、試合は終了。「みんな、楽しめたかな? 今日はありがとうございました!」の声に、子どもたちからの拍手がわき起こり、2時間弱のドッジボール教室が終わりました。

いかがでしたか。今回は「初心者向けクラス」の授業を駆け足で見てきましたが、ここに書き切れないほど、ドッジボールがうまくなるヒントがありました。興味がある方は、近くで同じような教室があったときに参加してみてください。

笑顔が絶えなかった教室風景
参加者の一人、麦島昊樹(こうき)くん(9)はお父さんに「今日でドッジボールがうまくなった!」と報告。父・広隆さん(42)は「スポーツセンターの掲示場をみてイベントを知りました。子どもは普段、サッカーをやっているのですが、今日は親子で楽しめたのでよかったです」と満足そうに話していました。
「ほめてあげてください」
最後に、講師の2人に話を聞きました。小学2年生からドッジボールを始め、アジア大会の優勝に貢献した経験を持つ森口さんは、終始、子どもたちのお姉さん役といった感じで指導を行っていました。
―教えるのが上手ですね。子どもに教える際、気をつけていることはありますか?
基本的に柔らかい言葉を使うこと。あとは、「合言葉は~」とか、「一つ目は~」とか、子どもの注意を引きやすい言葉を使っています。

参加者と記念撮影をする小池さん(右)と森口さん
―おうちで子どもにドッジボールを教えるとき、アドバイスはありますか?
保護者の皆さんにいつも伝えているのは、ほめてくださいねということです。熱心に教える親御さんほど、ここがだめだ、こうしてほしいとか、親の気持ちの方が大きくなってしまいがちですが、子どもが怖がってしまうのが、一番よくないパターンです。ドッジボールは当てられたら終わりではなくて、外野でも活躍できる。当たったとしても、かっこよかったよとか、声の出し方よかったよとか、必ずほめてあげてください。
―ドッジボールの魅力ってどういうところでしょう?
ドッジボールって、大きい小さい、体格にかかわらず誰でも活躍できるスポーツなんです。バレーボールとか身長が高い方が絶対に有利ですよね。でも、ドッジボールでは、体格がいいと、球は速いけど、当てられやすい。体格が小さいと球は速く投げられないかもしれないけど、かわしやすいんです。体格の大きい小さい、生まれ持った才能に関係なく活躍できるのが一番の魅力ですね。だから、体の小さい子がエース、キャプテンってチームがよくあるんですよ。
夢は親子で世界大会出場
一方、小池さんは2022年、エジプトで行われたマルチボール(複数のボールを使うドッジボール)のワールドカップ混合団体で銅メダルを獲得。日本ドッジボール協会のドッジアドバイザーの資格も持っています。
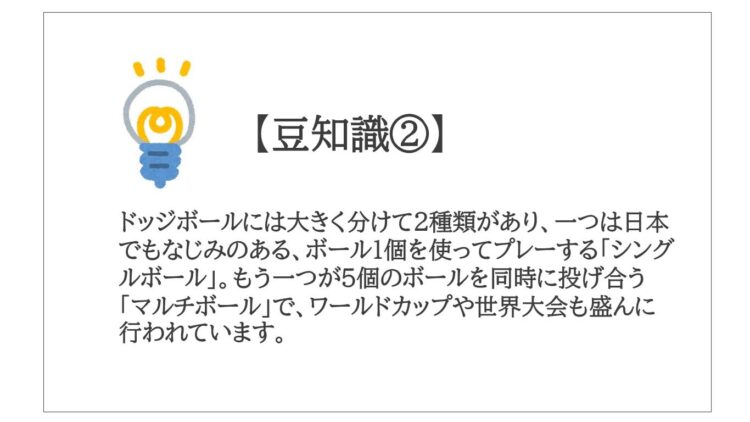
小池さんはこんな話をしてくれました。
親子で楽しめるのが、ドッジボールの魅力です。僕の家族は女の子が2人いて、上の子は4月に中学校に上がるのですが、今年の1月に台湾で行われた国際大会に一緒に出場しました。僕の夢は子どもと一緒に世界大会に出ることです。親子で世界大会に出られる競技って、あまりないですよね。
―確かにそうですね!
あちこち体が痛いですけど、親子で夢を実現できるように、今は頑張っているところです。

最後は笑顔で記念写真
家族で楽しめるドッジボール。この機会にぜひ、トライしてみてはいかがでしょうか。
取材協力=コナミスポーツ
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい












勉強になりました