PTAは「人権問題の警報が鳴りっぱなし」 自称”改革の負け組” 川端裕人さんに聞く現在地

〈インタビュー編・中〉

この10年のPTAの変化について振り返る川端裕人さん
良心を放棄しないとやり過ごせないような現場
―改革に失敗したのは、なぜなのでしょうか。
周囲を納得させられませんでした。「入退会は自由だ」と僕が言っても、役員ですら「聞いたことがない」という人ばかりで、説明しても「そんなはずはない」「そうは言っても現実は違う」と言われるような状況でした。「そんなに不満なら、転校する手もある」という提案も受けました。
委員のなり手がいなくて強引に決めざるを得ない状況を止めようにも、かつてその「被害」に遭った人たちが今度は「加害」に回ります。人の嫌な面をたくさん見たし、自分自身も嫌な面を見せたと思います。良心を放棄しないとやり過ごせないような現場で、精神的にもつらかったですね。「苦労したけれど、いい経験だった」とポジティブにはとても振り返れません。だから、「負け組」と言っています。PTAで良い体験を一切できなかったという意味で。
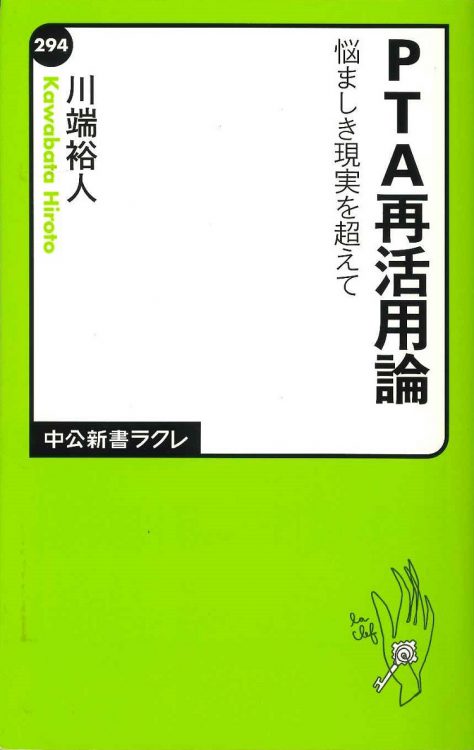
川端裕人さんの著書「PTA再活用論」
「入退会自由」整えても、差別や排除は絶えず
―この10年で何が変わりましたか。
一番は、当時は認識すらされていなかった「任意加入」の原則、つまりPTAは入退会が自由だということが広く知られたことです。背景には、途中で挫折した人を含め、各地で上げ続けた声の積み重ねがあると思います。今はPTA役員や校長でこの原則を知らない人は、まずいないんじゃないでしょうか。「入退会自由」とはっきり打ち出し、加入届を整備したところも増え、早期に対応しなければと考えているところも多いでしょう。
もっとも、知らないわけじゃないけれど、特にそれが問題とは思わない人たちは普通にいると思います。それまで学校にもPTAにもかかわったことがなかった人が、いきなり会長になって、PTAに適応できている役員たちとしか接触がない場合など、「入退会自由と言う人はアンチ(対抗勢力)」のように思うかもしれません。
そんな場合、「入退会自由」という形だけを整えても、実際の運用は前と変わらないということもあります。それどころか、登校班外しや、PTA主催のイベントに参加できないなど、非加入の子どもへの差別や排除はあちこちから報告されていて、本当にひどい話だと思います。そういう排除の論理に至ってしまう人たちは、その人たち自身、追い込まれてしまっているのかもしれませんが、実は、一番、PTAみたいな団体をやってはいけない人たちです。PTAは加入・非加入を問わず、全ての児童・生徒のための活動をするという、団体の本来の趣旨を理解していないのですから。

非加入を選択した人は、適正化に貢献している
―そんな中でも、非加入を選ぶ人が出てきています。
「やらない」という選択をした人は、流されるままに会員であり続ける多くの人よりも、PTAの適正化に貢献していると思います。非加入や退会を選ぶことで、これまで見えなかった問題を可視化してくれているわけですから。現場に踏みとどまってPTAを改善しようとする人たちと同じくらい僕は尊敬し、感謝しています。両者の問題意識は重なる部分があり、状況が違えば互いの立場は逆かもしれないんですよ。
―「改革」の要望にも、いろいろあります。
今の会長らは非常に厳しい立場に置かれています。任意加入の周知など「まともな運営」が求められる一方、「コミュニティーを活性化するような活動」も同時に求められているわけですから。「PTAが中心になって、保護者や地域の強いつながりをつくる」というような理想を語る人もいます。そういった夢を見ること自体は、僕は否定しません。
ただ、日本のPTAは、ずっと人権問題の警報が鳴りっぱなしのまま来てしまっているんです。現状では、とにかく、「やりたくない人」「できない人」の緊急避難の道を確保してから、夢を見てくれと言いたいですね。
その上で、「やりたい人」「できる人」に機会を開くような活動からこそ、力強いコミュニティーができるのではないでしょうか。僕自身、保護者として学校とかかわった十数年のうちで、子どもたちのために現実的に役立つ活動ができたのは、PTAではなく、読み聞かせのグループや、カジュアルな学級単位のLINEグループなどがきっかけになったものでした。特に、学級崩壊、授業困難、担任によるハラスメントの問題に対して、PTAは無力でした。

いまだに「入退会自由をうたうと担い手がいなくなる」と心配する人がいますが、それでPTAがなくなった報告はありません。むしろ「PTA、強すぎ」という印象です。同調圧力的な要素は相当しぶとく残っています。
幸い、この10年間、各地でPTA運営の改善の事例が増えてきました。参考にできる経験の積み重ねがあるのは心強いことです。ただ「任意加入の周知」の仕方一つとっても、導入を目指す人同士で踏み出す方向や順番が違うと、互いに批判しあうこともでてきます。進め方に正解はなく、根っこの部分の問題意識を共有して進んでいくことが大事だと思っています。
川端裕人(かわばた・ひろと)
1964年、兵庫県生まれ、千葉県育ち。2007年から世田谷区立小学校のPTA副会長を2年務めた。都立高校PTAでは広報委員の経験も。小説は、少年の成長を描いた「川の名前」(ハヤカワ文庫JA)、「今ここにいるぼくらは」(集英社文庫)など。
PTAは「実は戦前組織の’’看板の塗り替え’’です」 岩竹美加子さんが指摘する悪弊の背景
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい












癌で4年間闘病中ですがPTA役員とクラス委員に選出されたことがあります。
我が子の通う小学校では、病気、介護等を理由に役員免除の申請ができず、立候補者がいない場合には、くじ引きで決定する、そんな選考方法です。
私は選ばれましたが、2回とも辞退を申し出ました。
ただ、辞退させてもらうために、PTA会長、役員選考の方々に、自分の病気の説明をしなければ理解してもらえず、とても苦痛でした。
癌で闘病中でも端からみれば、健康そうに見えるのかもしれないから、説明しよう、そんな気持ちで話しましたが、PTAの方々が今後個人情報保護を守ってくれているのか、いったいどうやって確認できますか?噂話が広がるのでは、と心配でなりません。
人権なんてないですよ。退会理由を役員の保護者にお話しして賛同を得るなんて笑っちゃう誰にも言いたくない事を言わなければ免除されない事自体がやばいよ。まして賛同を得るとか、なんの権限があって人のプライバシーを暴露しなきゃいけないんだ。みんなやってる事だからやらない理由をお知らせするのは当たり前とか言うのは、やめたほうがいいですよ。一人だけ逃れるなんて許せないとはなんですか?
専業主婦ばかりの時代は終わりました。
例)1クラス35人2クラス×6(学年)イコール420人、だいたい1割40人位がPTAに意識が高い親。この人数でPTAを回す事が理想。
育児、仕事、介護、家事等、優先順位は個々で違うが420パターンあるのに子供を人質にとりポイント制で縛るのは間違い。
「PTAくじ引き当選、日本死ね」できない親には意識高い系が扇動し、そういう時こそ直ぐ団結しポイント剥奪しろと圧をかける。
みんな違うのが当たり前。その時その都度、1時間だけ、お願いしますとボランティアを募る。1年間の縛りも気が重い、、、もっと気楽に楽しく参加できる工夫が必要。今の現状では、ますます少子化になるとおもう。PTAストレスはどのように解消されますか?コロナだからこそ、いらないストレスを増やさないで無駄は無くすべき!
義理母が私達は苦労した。だから嫁も耐えろみたいな雰囲気のPTAは壊すしかない。家事代行サービスのようにPTAも民間委託したらいかがでしょう?
やる気のある60代70代シルバーを積極的に採用、国の予算をPTA給料制にあてる等、、、。
ざっくばらんに女性達が本音で話し男性達も巻き込み対等に事にあたれる良い案がうまれることを切に希望します。
保育園のPTA役員を1年だけやりました。
古参の役員経験者たちが何年も役員を続けている園だったので仲が良い人と新規の人の溝が深かったです。
古参役員は上の子の小学校のPTA役員が当たらないように何年も続けているようで、その役員たちと別の学区ではありますが小学校PTAも闇が深そうだと感じ将来的に入会を躊躇うと思います。
コミュ力が低いので役員は一年間苦痛でしたが、コロナの影響で軒並み行事が中止になったのでかなり助かりました。
私は新規だったので気づいていない事もあるでしょうが、無くて良いものがたくさん省かれ、PTA活動については良い一年の活動環境だったと思います。
正直、このままPTAなんてなくなれと思っています。
ボランティア活動は好きでいろいろ参加しているのに、PTAは強制的な雰囲気や同調圧力が本当に苦痛です。
学校側が、とにかく保護者に何かしらやってほしいんだなと強く感じます。このコロナ禍なのに、PTA活動を先生が押してきます。「配慮してます」と口では言ってますが、頻繁に学校に足を運ばせ何かさせる気満々で、行政と学校教育との間にズレを感じます。体の弱い高齢者も家に居ますし、出来るだけ感染しないように生活しているのに、学校側が壊してしまっています。クラスターでも起こったらどうするつもりなんでしょうか。国から教育委員会?学校?に向けて、PTA活動を自粛するように呼びかけるしか無いんじゃないでしょうか。
今年度会費を上げたのに、コロナの影響なのか余ったらしく、その剰余金と長年積立ててきた記念事業の積立金を流用して、配付されるタブレット端末を有効活用するために大型ディスプレイを購入するという驚くべき提案がなされています。予算の仕組みを理解できない本部の思いつきだと考えられます。総会はただのセレモニーなので原案どおりに決定するのは間違いありません。この状況だと会費は上がり続けます。
私は4年前に小学校の副会長を経験しましたが、2月に会長と喧嘩して辞任した経過があります。昨年は、その経験を踏まえて正常なPTAに変えようと中学校の会計に挑戦してみましたが、コロナ下でも従来どおりに業務をこなすことしか考えない役員と感心のなさそうな校長、PTAは任意のボランティア団体だと知って、すぐに辞任し退会しました。そして、先日は小学校のPTAも不公平だと感じている自分に気がついたので退会しました。
問題提起のつもりで一人で戦っています。
本部役員を1年間やった者です。承諾したときは、「週に1回2時間位、1年だけ」とのことでしたが、選考委員の言葉を信じてはいけなかったのです。週に2回午前いっぱい、場合によっては午後まで延長することもしばしば、作業を自宅への持ち帰ることも多々あり、総会やバザー前後は毎日のように学校に詰めていました。
フルタイムの仕事をしながらだったので、目いっぱいの有休や半休を使って、職場にも沢山迷惑をかけ、家事をする時間が減り、持ち帰り作業を夜中に行い、慢性的に睡眠不足、何より自分の子どもと過ごす時間が減りました。約束通りの1年で辞めるときも、「皆2年以上はやりますよ。」「2年しないとPTA顕彰の対象になりませんよ。」と非難ごうごう。
PTA活動の多くは、昨年の踏襲。子供たちのために本当に必要な活動を行おうとするのではなく、不公平感を無くすため(全800名の児童の保護者が卒業までに必ず役職につくために)、仕事や役職を維持しているような状態でした。「パートを休んだから、3000円減収なの。」といいながら1000円に満たないベルマークを切っている。メール配信で良さそうなプリントを大量に印刷仕分けするために集められた委員達。余った大量の懇親会のお菓子を各家庭に配り歩く。
一部のやる気があり他にもそれを求める人、一部の絶対にPTA活動をしたくない人、大多数の事なかれ(私も含め)の人、全ての思惑が交差することなく散逸し、終着の決まった台本通りの会議・活動が続くのです。
私のPTA活動は終わりましたが、今後もPTA役員を担う方々がおられます。
小学校内でPTA活動の改革を声高に叫ぶ勇気のない私でしたが、改革の必要性は感じました。
わが子の小学校では、このコロナ禍で、総会、バザー、セミナー、懇親会等ほとんどの活動がなくなりましたが、特に困ることはありません。
コロナ禍の今は、PTA活動の抜本的改革のチャンスです。
会員に無理のない、そして原点に立ち返り、本当に子どもたちのためを考えた活動に舵をきって欲しいです。
一度だけ学年委員長をやりました。シングルマザーなので、会議や行事の仕切り等で仕事を休まなければならず、役員をやった年はお給料が減りました。何年も前から「女性が輝く社会」を謳っているのに、とても矛盾を感じます。PTAは働く親にとって死活問題にもなります。令和の時代には合っていません。
ヒラ役員だった時、集まりのために会議室を予約していたのに、前日になって「学年委員の方が上なのよ!」と言われ、会議室を奪われました。
「会議室を半分貸してもらえませんか?」と聞いたところ、かなり怒鳴られビックリしました。
また、前例踏襲主義で、報告書のフォーマットを変えると怒られるようです。
何かを改善することは禁止されており、二度とかかわりたくない組織だと思いました。
PTAの問題、というより学校全体の問題なのかもしれません。
小学校の先生方と話すと、論理的な話ができない人が多く、根拠を示せない人が多いように思います。
子どもたちもそれを見抜いているように感じます。
学校のP T A同様、保育園の父母会も全く同じで、P T Aや父母会って何なのか疑問です。
役員を経験しましたが、総会で意見しても結局、P T Aを変える事は出来ませんでした。来年に持ち越したり、保護者も役員決めは強制してでもやらないといけない、仕方ないとの認識の方が多かったです。
任意といっても、結局、入らないとこどもがイベントに参加できなくなる現状があるため、親は入らない選択が出来ません。
ボランティアなのに、何故?
こんな組織なくなればいいのに、と思います。
報道の力を借りて、本当にPTA制度、見直して欲しいと思います。私の住んでいる東京都23区内ですが、子ども会に入らないと登校班に入れない決まりがあり、その事にずっと疑問を持って、教育委員会などに掛け合ったり、自分なりに動いてみました。そこでたどり着いた事は、文科省や行政、教育委員会はPTAに法律上 指導できないんです。
これが大きな問題だと思います。何故、保護者がこれらの組織が介入できないPTAという団体の活動に強制させられるのでしょうか?
PTAや子ども会を、公教育に関与させるのをやめて欲しいです。文科省にお願いしたい。PTA会費で、卒業証書の筒を買うのは何故ですか。そのせいで、加入してる児童しか筒を貰えません。実費を申し出れば、例えば未加入者が1人しかいなかったら、その1人のための作業が発生して、面倒くさいなぁという役員もいるんですよ。
PTAはボランティアなんですよ。児童を公教育の中で平等に扱えない事が発生するなら、もう、PTAは学校の中で活動してはいけないと思います。そこは、文科省が各自治体に示すべきですよ。コロナで休校になり、色んな問題が浮き彫りになっているにもかかわらず、まだわからないのでしょうか。
児童の権利って何ですか?公平性ってなんですか?くじ引きで役員強制しても公平じゃないんですよ。だったら初めから、入らない選択肢も保護者に下さい。
入学の時点でも公平じゃないです。給食費と引き落とす口座の手続きを学校に提出して下さいと学校から手紙を配布されたら、みんな提出しますよね?それでPTAに加入に同意したとみなして良いのですか?私はそうは思いません。ならば、活動を強制しないでください。加入することと、実際に、活動することは別なんですよ。
子どもを区別されたくなかったら、PTAに加入しろ、という、日本の公立小学校、おかしいと思います。入らない選択肢をした母親が悪いのですか?現場はそうなっています。だから、やりたくないお母さん同士で、毎年、役員ぎめ苦痛です。
損害賠償請求が起これば、矢面に立つのはPTA役員ではないですか?本当にこの仕組みはおかしいですよ。誰のための組織なのでしょう。見直すなり、廃止するなり、いい加減に変わって欲しいです。
PTAは日本では、単なる私的団体の位置づけなので、非会員の児童を区別する事は可能だそうです。子どもが地域の子ども会を辞めたら登校班で通えなくなったので、PTAについて、調べてみました。
本来PTAは児童は会員ではなく、保護者と教員から成るボランティア団体です。でも現実はどうでしょう。役員は強制、任意説明どころか、入る入らないの選択肢もなく、基本みんな会員ですよね?東京都ですが、私の住んでいるところはそうです。
ボランティアなのに、役員強制、やりたくないのが本音の保護者で活動するPTAって何なのか?みんなが登校班で通っているのに、親の未加入で登校班から外された子どもの気持ちを会員の保護者はわかってますか?退会した親が悪いのですか?
児童を区別しても問題ないという団体が、学校の施設を使える日本の法律、文科省に対して大きな疑問を感じました。こんな団体とは関わりたくないと思い、コロナが終息したら、PTA退会しようと決めました。
せっかく国立小学校に合格できたのに、PTAの強制力が強くて辟易しています。
役員決めを兼ねたPTA発足式は強制参加と入学書類に明記されていました。参加しないと学校生活に必要な備品を受け取れなくなります。学校の方針に従わないと二言目には「転校して下さい」と言われます・・
国立なので自治体の教育委員会に相談することもできません。こんな時代錯誤のやり方は強要罪、脅迫罪にあたるのでは?
今年はコロナウイルス対策で集会の中止が求められているのに、発足式が強行されました。学校そのものも閉鎖状態なのになぜでしょうか? 学校生活や各家庭の健康よりPTAの方が大切なのですか?
国立小学校は社長一族など社会的に影響力のある家庭の子女が比較的多いのに、行動する人もおらず、改革もされていません。「学校を助けるためだから」と、逆に宗教のようになってしまっていて恐ろしく感じます。
この4月に新一年生になる女児の母です。
私は軽度の鬱と注意欠如障がい、加えて更年期障がいと格闘しつつ、単身家庭のためフルタイムのパートでなんとか仕事を続けて生活しています。
高齢出産だったため、私の両親ともに高齢であり、加えて父は障害者手帳1級をもつ身体状態で、母は長年 重度の統合失調症を患っており入退院を繰り返して生活している状況です。(父の強い希望で私たちと同居はしていないため、私や娘たちが通いで適宜サポートしています。)
新一年生の子の年の離れた上の子は、発達障がいがありI.Qが85とボーダーのため、定型発達児に比べ生活面や精神面での直接的かつ具体的なサポートが日々必要な状況です。
自分の置かれた状況の中で、私たち家族はそれぞれ自分なりではあるけれど、必死に頑張って生きています。この必死というのは決して大袈裟ではないのです。定型発達者や健常者の方が普通にできることが普通にできないけれど、それでも社会に参加して生きていかなければならないし、普通の人のように社会に参加していきたいと願って頑張っている。けれども身も心も消耗寸前、綱渡り状態の毎日なのです。
こんな生活環境及び精神状態であっても、PTA役員をやらなければならないのでしょうか┉。
働く能力があって継続して働けているからといって、鬱や注意欠如の症状が軽いわけではないのです。(これは発達障がい当事者でないと理解しがたい事実だと思いますが。)
PTAの存在自体を否定するつもりはないし、役員をやることができる自分だったらどれだけ良かっただろうとも思うのです。でも、私には無理です。
それぞれの家庭の諸事情や家庭環境を考慮した上で役員を決めることは簡単なことではないし、それらを決める上での選考の基準を定めることすら難しいし、その上での公平性の保持なんて考えただけで不可能なことだと思います。でも、私には無理です。
精神的にも肉体的にも経済的にも、人的環境面、時間的制約、全て私には無理なのです。
PTA退会を申し出た保護者が、何度も校長に呼ばれて、やめないよう説得され、結局やめられなかったそうです。校長がこういう事をやっていいのですか?報道されてる事と現実が全然違います。誰の言ってる事が本当なのでしょうか?
PTAを退会したら、子どもを区別するとはっきり説明がありました。これのどこが子どものためのPTA活動なのですか?PTAはボランティアですよね?
いつになったら、本来の組織の在り方に変わってくれるのでしょうか?本当にないと困るものに限定して、やりたい人がやれる時に集まって、集まった人数でやれる活動に縮小すべきです。
ほとんどの学校のPTAの運営方法が、人権侵害だと感じます。違うのでしょうか?東京都です。
学校にも一般企業と同様に、法律を介入させて頂きたいですね。
私の小学校では何年も同じ人がやっていました。 その女帝はやりたい放題で、規約まで変える始末。その子分と共に何年も居座りました。その子分は今や、学校で働き、永遠にその学校を仕切るつもりです。校長、副校長もいいなりでした。
先生は異動になっても、PTAは変わらない。もう淀む一方です。
我が家の子ども達の通う公立小学校は1人の子どもにつき1委員の学校です。私は1番下の子どもの入園に合わせて5年生の長男の学年委員に立候補しました。委員の中で私だけが専業主婦だったため半ば無理矢理委員長にされてしまいました。そして昨年12月頃から今年度の委員決めに動いていますが1人も良い返事をいただけていません。どこにも明記されていませんが、次の委員は現委員長と副委員長が探すという暗黙の了解があります。何人もの方に頭を下げてまわり、同じ保護者なのに嫌なセールスマンが来た時のような態度でお断りされたり無視されたり。静まり返る懇談会の事を考えると動悸や震え、汗や吐き気が止まらず、体調を壊してしまいました。
見かねた夫が校長に話をしてくれていますがPTAのことはPTAの中で…とのらりくらり逃げています。
やっと校長と会長と話をする場を設けることができましたが、どうなることやら。
お世話になります。
来年度よりPTA本部役員を担うこととなり、先日1回目の打ち合わせに参加致しました。
私が役員を引き受けた背景として、子供が4人いること、最低でもそのひとりひとりにつき1回ずつ役員をする必要があること、お世話になる学校に対して子供たちのためになることをしたいという思いがあったこと、本部役員をした場合はその後の役員活動は免除となることがあり、それなら少し大変でもやってみようと思い、また主人も家族も協力すると言ってくれました。2年間の任期をしっかり務めたいとの思いで引き受けました。
しかし、実際のところ本部役員経験も年数のカウントのみで、免除はなくなったということでした。本部役員をしたからといってそれは不公平ではとの声があったようです。
また小さい子を連れての参加はできない部分が多いこともあいまいでした。
それからそれぞれの役員の分担の物まで、本部役員へ回ってきたりと、負担が大きすぎると感じ、引き受けることにしたものの、不安しかありません。
これから2年目の本部役員の方に相談してみようとは思いますが、今後役員を引き受けてくださる方のことも考え、やはり免除、子連れ参加可能の部分はしっかりと規定として設けてほしい思いです。
任意という事で申し出れば未加入は選択できました。しかし、PTA主催のイベントには子どもは参加出来ません。また、プリント配布物、卒業の饅頭なども全部渡せません、と言われました。実費の支払いの申し出は受けてくれるとの事だったのですが、実際は会員皆で買ったほうが安い物などあるという理由で、未加入者だけ個別に対応するのも面倒だみたいな話もありました。
ニュースなどでは、子どもを差別してはならない、これは法律で認められていないと報道されていますが、実際に現場で差別を受けています。
どちらが本当なのでしょうか。
もし本当にPTAの対応が間違いなのであれば、文科省や教育委員会で何とか対処して頂けないでしょうか。保護者間で本当に解決出来ません。文科省で今後も対応していただけないのなら、弁護士さんにお願いしようと考えています。
くじ引きの拒否権はあるのですが、そのために説明をさせるのが、人権侵害でしかありません。私は子が一年生で早々に本部役員を引き当てなんの知識もなくやっていたのですが、くじ引き抽選会の準備で、アンケートに書かれた複雑な家庭の事情を目にしました。
自身の精神疾患、子の重度障害、失業などの経済的な問題、これらをわざわざ告白させるのです。本部役員にしか見せないといっても家庭数が250程度の小規模校では半数は本部役員になるので、秘密でもなんでもありません。
また、父子家庭は免除なのに母子家庭はダメ、女性しか役委員になれない。もしくは男性が参加するなら会長。という暗黙の女性差別があり、女の労働はタダだけど男労働は尊いと言わんがばかりのあり方に、憤りをかんじました。
女性校長にパートにでたら1000円は稼げるところをわざわざありがとうございます。と言われた時も公務員は無償パートおばちゃんくらい思ってるんだと思いました。
また、あまりにもアナログな仕事っぷりにイライラしても一切の変更修正は禁止、ちょっとでもミスがあれば組織ではなく個人に電話攻撃しかもミスした本人ではなく気の弱い主婦の役員さんを狙って一時間も説教してくる。そうなるとその人を庇うために仕方なく言うことを聞いてしまう事の繰り返しで改革なんて手のつけようのない『終わってる』クズ組織だとわかりました。
くじで1度も経験の無い委員の委員長をすることになりました。致し方ないので業務の引継ぎをしていただきましたが、業務内容が煩雑でとても出来そうにない、と数日眠れなくなりました。協力してくれる副委員長もおらず母親同士のつながりどころか人間不信になりました。なんとか1年やり遂げましたがもう2度としたくありません。小学校のボランティアも(月に数回程度)行っていたのですがもう小学校に行くことにも嫌気がするので来月いっぱいで辞めるつもりです。周りで役員になりたい、という方は皆無なのに続いているこの制度が不思議でなりません。本当に必要なら必要経費として請求してもらって構わないので、保護者を強制的に働かせるこの制度を廃止してもらいたいです。このような煩わしいことが山積みなので少子化も進むのではないかとまで勘ぐってしまいます。
多摩地区にある都立高PTAの選考委員です。PTA事務員が非常勤で雇用され、金銭の管理、印刷、配布等の負担が少なく画期的と思います。しかし役員候補を自推、他推の無記名投票と、入学前のアンケートで過去の役員歴を書いた人がピックアップされ、互選会に招待されます。住所と電話番号を副校長から受け取り、選考委員が手分けしてリマインダーの電話をかけます。つまり学校も認めているということです。
番号一覧はグループLINEで届きました。あくまでもリマインダーなので勧誘やお願いはしませんが、苦情を言われることも多いそうです。電話は指定された3日間✖️2時間(19〜21時)の間で自己負担です。さらにこの活動内容は他言無用と言われています。初めから知っていれば引き受ける人は少ないことでしょう。
また介護や持病等の事情は不幸自慢だと言われてしまいます。唯一家族が揃う時間帯なので夫と子どもも納得しておらず、辞退するつもりです。
学年委員は様々な父母と知り合い、和気藹々と楽しかったのに、選考委員は役柄が非常な人が多く残念です。
①入学前に、電話で退会したいですと先生に伝えました②家庭調書の何か他に伝えたいことがあれば書いて下さいの欄のところに、退会したいですと書きました③pta総会で、皆の前で自分一人だけ退会したいと言いました。会長も先生もいました。
これだけしたのに、退会してませんでした。自分自身その事実を知ったのは、卒業間近の時でした。
在学中に2回、役員をやることになっています。ポイント制で、強制です。役員を決める保護者会に参加できない場合は、欠席の場合も役員になることを承諾しますという紙を出さなければなりません。いやいや役員になり、何とか役を終える方と、役員になっても活動を全くせず無視を続ける方もいます。そのため、大きな不公平感や不満を多くの方が抱えています。平日夜乳幼児のみを家において、参加しなければならない運営委員会、共働き世帯には、不可能です。
今年初めてPTA役員をしています。やってみて思うのはやはり活動内容に意味がないよう、ということです。
外から見ているとPTAって何やってるのかわからないのに同調圧が強そうで、よくないイメージしかありませんでした。くじに当たって仕方なく関わっていますが、そりゃあこんな中身のないことばっかりしてたら内緒にしたいよな、オープンにしたら余計誰も寄りつかないもんな、と思います。
娘の学校では、おなじみの1人1役、活動できない人は家庭の秘密暴露、次期執行部役員は「推薦」という名のなすりつけ合いです。私の学年では「そんな無責任な推薦できません」と回答したら「あ、そうですか」とあっさり受理されましたが、それって断れない真面目な人を搾取するやり方だなぁと思います。
そうやって押しつぶされた人が「やらないのズルい」となるのかな、と思いました。
よく会費払ってないんだから、非会員なんだから、区別されて当然だろ、という意見もありますが、それは違いますよね。そもそも、PTA会費と給食費を一緒に引き落としてること自体、場合によっては違法では?と思います。
PTAやめると、卒業のコサージュが貰えないという小学校が、埼玉県で実際ありました。それだってPTA会費で買わなければいいだけの話ですよね。学校でコサージュ代を集金袋を子どもに持たせて、回収したらどうですか。?
わざわざ非会員、しかも児童は会員ではないのに、そうやって、区別するのって、結局、PTAを強制してるだけだと思います。
東京都墨田区の公立小学校です。子ども会に入らないと登校班に入れません。PTAや子ども会の任意団体が登校班編成や旗振りをしていても、子どもは義務教育で学校へ行っているのだから、親の非会員.会員で区別してはいけないと思います。区別するなら、学校がやるべきです。
任意団体なのだから、入らない選択をする世帯があって当たり前なのに、入らない選択をした世帯の子どもに不利益が生じるのはおかしいと思います。
学校が集団登校を実施を選んだのではないのか?PTAが独自に登校班編成を行っているわけではないはずです。学校は関与しています。こういったトラブルを放置して、保護者が訴訟など起こせば、矢面に立たされるのも、保護者なんです。PTA会長といえど、保護者ですから。最後は保護者同士で争う事になります。教育委員会や学校、行政のシステムはずるいと思います。
だから、入学すると全員がPTA会員に当たり前のようになっていますが、今の時代、入退会の意思を保護者に確認する事は必要な事だと思います。PTA役員になったら尚更気をつけるべきと思います。
トラブルが起こっても行政や教育委員会はPTAなどを指導出来る立場にないからと言って助けてはくれませんし、保護者同士で解決してくださいという事になります。
愛知県豊橋市で来年度からイマージョン教育を始める小学校があります。八町小学校という所です。現在は募集を締め切りましたが、申込にはPTAに協力する事、地域の自治会活動に協力しルールを守ること、小学校のルールを守ることの3つを1枚にした同意書にサインをして、そのほかの書類と共に教育委員会に提出しなければ申し込めない仕組みになっていました。子どもの入学を人質に、PTAへの強制加入せざるを得ません。説明会ではわが校ではPTA加入は絶対です、の一点張りでした。国の補助金を受けて、未来へ向けて新しい取り組みをしようとする学校が、市と、教育委員会と、地域住民が一体となって任意団体であることを一言わず、従来の在り方に口をつぐんで協力する人しか受け入れようとしないのです。今でも平然と、市の教育委員会HPに書式が掲載されていると思います。公立の小学校で、こどもを人質にとり、任意団体に強制的加入する同意書が入学の入り口なのです。子どもにより良い教育を受けさせたい保護者は犠牲になるしかありませんが、これは違法行為なのではないでしょうか。行政が受付の窓口となっているのですがら、豊橋市がPTA強制加入を容認し協力しているといっても過言ではありません。ひどい、と思います。
過去に子ども会会長、現在PTA本部役員をしています。どちらも、自らがやる意義を持って役員になる方は僅かです。それを責める気は全くありません。事情や考え方は人それぞれで、同じ思考の人ばかりでは、人間社会に発展はないですから。
私自身は、大変だったけど(時間のやりくり、人間関係など)学んだことの方が多くやって良かったと感じています。(もちろん後悔もいっぱい)
実際は、担当する内容によっては、やはり専業主婦、もしくはシフト調整できる仕事の方でないとこなしきれないものも多々あるのが現状です。
働く方、専業主婦の方、どちらも考えがあっての選択です。働いているから子供関連を疎かにしているわけでも、専業主婦だから時間が余っているわけでもないのが大多数だと思います。
次年度役員選出で本部が「決まるまで」と話すのも、悪意があってではないことをご理解いただきたいです。決まらなければより時間(日を用意して)を割くことになります。お互い不満を言い合うのは容易いことです。ならば、少しでも変えて行くことを大切と考え、積極的に関わり、会が存在する本来の意味に近付けられる様知恵を出し合ってみるのも一つかと考えます。
窓口がもっと開かれるといいですよね。
良い意味で、これだけ多忙な生活をしていても、こんな方法でこんなパターンができる。実行するのはエネルギーを使いますが、発言だけでは何も変わりません。一人で何とかしようとしても難しい問題です。行動に移されてきた方々を尊敬いたします。
他者(年齢層も多種多様ですしね)を思いやり、現代の叡知をフル活用する。
何のために存在している会なのか、多くの人が知る必要がありますね。
行政の方も、人任せはそろそろ終わりにしませんか?人間には、失敗も甘えもあります。悪いこととせず、活かせたらと自分自身へも願います。
ズバッと感がなくすみません。
PTAの交通郊外委員を子ども会から選出しています。子ども会から選出なので、PTA役員をやった事にはなりません。また、子ども会に入らないと集団登校できません。退会したら、登校班から外れます。この子ども会は、地域のお祭りのお手伝いは(子ども会の縁日)強制で、法事などの理由があっても、家族間で都合をつけるなりして、不参加はダメです。子ども会に入らない児童は、保護者が毎朝登校に付き添うよう、学校が支持しているところもあります。
PTA役員になると、仕事をされてる方が多いという理由で、夜7時から9時に子どもを連れて会議に参加しなくてはいけません。祖父母やご主人の協力が得られないと、そうするしかないです。
PTAって、そこまでして母親が都合つけてやらなければならないものなのでしょうか?昼間仕事して、夜子どもを連れて出たくないし、昼間仕事をしていなくても、この時期帯に出たくないです。みんな都合つけてやっているから、出来ません、出来る事をやるという選択肢がない。親同士で話しても解決出来ない。
PTAはボランティアなのだから、やらない選択肢が欲しい。退会届けが何故ないのか疑問。具体的に何をやるのかわからない仕事に、立候補できない。ならば、PTA会長は保護者全員に具体的に説明し、入会申仕込み書を作り、入会した保護者は責任持って仕事をするべきで、子どもに不利益が生じるような活動に加担するのはやめて欲しい。子ども会辞めたら登校班から外され、旗当番などもやらなくなったのに、PTA会員でいる意味がわからなくなったから、PTAも退会しようか悩んでいます。PTAイコール子ども会で学校運営されていますから。
こういった事を学校や教育委員会、文科省や法務局、議員さんにも相談したけど解決出来ない。そもそも学校や行政は社会教育法により子ども会は指導できないといって、問題が起こりお話しても仲介してくれない。神戸の教員いじめ問題ではないが、学校は法介入できないようになっている。一般企業なら罰せられるのに、学校は罰を受けない。個人情報違反をしても教育委員会から注意を受けるだけ。文科省も子どもが死ななければ動かないです。だから、いじめや自殺が起きてから謝罪して終わりなんです。今回、子どもが登校班から外されてから、様々な教育機関に話をして、一番感じた事です。教育委員会の存在意味などわかりません。文科省に電話した時も、PTAが会員と非会員を区別してもやむを得ないし、 差別ではないとおっしゃっていました。
これが日本の教育現場の実態です。
ここを何とかしなければ、PTAも差別もなくならないと思います。毎年PTA役員決めで候補者がいないと、決まるまで終われませんと進行役の保護者に言われて、重い雰囲気になるのが本当に苦痛です。こんなPTA.だれもやりたくないですよね?
本当に必要な活動だけに限定出来ないのでしょうか。墨田区では漢字検定もPTAの仕事、校庭開放は子ども会の仕事。保護者は印鑑持参ですが。これは行政の仕事ではないですか。子どものためと言われて、社会教育団体の意味もわからず役員をやっている保護者が沢山います。そういう保護者、子どものためと言って、騙しているのと同じように思います。
時期役員の推薦委員長になりました。転校してきて役員についたこともなく、PTA内情も保護者のお名前もお人柄もわからない中で、時期役員を選出しお願いして回る、かなり疑問に思いながらも受けた役割、子どもの為と思いなんとか勧めています。
90パーセント以上の保護者がやりたがらないPTA役員…これではいつまでたっても良い運営は出来ない気がします。こんなにやりたくない保護者がいるなら、無くせば良いのに…と、単純に思います
PTA主催の行事は加入非加入のお子さんに限らず公平に扱う、ということには違和感を覚えます。
会費を払わなくても全員がもらえるものはもらえる、となれば、会費を払う人がお金も出し役員会もやり、というのはおかしいです。
小学校入学と同時に名簿が自動的にPTAにわたる。なんの説明もない。
今、PTA本部役員をしていて、改革を進めています。入会は任意である事、保護者が非会員となっても、子どもには一切の不利益を生じさせないを掲げて今年の4月から活動をしています。現在は活動を見直し、子どものためになる事を残して全保護者に対してボランティアを募ってイベントなどをしています。
次年度は、各委員会を廃止し、無理せず、出来る人が出来る時に参加するボランティア活動の場に作り変えるべく、邁進しています。改革の為に、今は大変ですが保護者がボランティアしやすい環境こそが、「子どもたちのため」に繋がると考えています。
私もPTA 運営委員を3度やりました。給食費集金方法変更提案をしましたが聞いて貰えず(自振だと他校で払わない人がいたという理由)翌春盗難事件で全国ニュースになりました。
昨年度運動会も変質者が入りニュースになる等、学校HP等の個人写真利用も現在校長、PTA 会長に代わってから事件や非常識と感じる事ばかり。PTAに関する問合せ先は、メールですら皆無です。
登下校の見守り当番を、当番制→ノルマ制に変更し平日勤務の私は、子供の体調不良でお休みした日についでにやる状態です。訴えても、話し合い等ならず、スルーされます。市の連合会問合せも、全く無回答。毎年30万の予算を一部のPTA 遠足費に利用も止めようと伝えているも、ほぼ無視です。今年度、中学で会長と連絡をとり退会することができましたが、私の希望している『入会届』を、年度始めに提出する事は検討されていない様子です。
私は小田原市ですが、県内の藤沢市は60%位PTA は解体したようです。そちらの市は、県内TOP校があり、中学受験の家庭も多いですが、小田原市は高校も殆ど市内にいるのが現状で、学力も県内では低い地域です。
PTA は良い企画ができておらず(会費の公平性が低い)飲み会ベースの方もいる、先生と仲良くする事で優越を感じたいとしか思えません。専業主婦の方が、広い視野を持ち企画する事は難しいと思います。
運動会等、教員だけでは賄えない行事の運営を手伝うのは理解できるし協力したいと思う。しかし、PTAバレーボール大会や家庭教育学級等、こどもが直接関わらない行事の準備や手伝いは(親睦を深める為という目的があるとはいえ)自分の仕事や子供との時間を犠牲にしてやる事ではないと思う。
また、今通う公立の幼稚園では作品乾燥棚や平均台など、園の備品をPTA会費から出しているが、本来市が整備すべきもの。おかしい。
親ばかりがPTAに対して異論を唱えていますが、本当に声をあげたいのは先生の方ではないかと思います。子供が属していないのにPTA会費は徴収され、無償で労働。更に自分の子供が通っている学校へもPTA会費支払。ひどい話だと思うけど、訴えてもPTAは会費欲しいから〜とか平気で言う。
随分、勝手な親が増えたと思う。子供を預けている以上、親は学校に協力する姿勢があっても良いと思う。一つの行事を行うのには、地域の人をはじめ、様々な人の協力がなければ成り立たないのだから。一度、役員をやってみると良い。それが良く分かるから。先生やPTA役員、委員へ感謝もせず、文句ばかり言う親が減ると思う。もちろん、日本語が話せないとか介護とか、其々家庭の事情もあると思うけど。
とにかく反対の声をあげ退会者を増やすことです。PTAにどっぷりもたれかかる学校は、言われないと気づかない、困らないと変えない、です
私もくじ運が悪くて過去に保体委員長を引き当てひどい目にあったことがあります。とにかく会議等都合が悪くて休むと委員長は責任があると責められ、うんざりしました。
今子供は6年生ですが中学ではPTA未加入で行こうと思っています。先日中学のPTAからの手紙を子供が持ち帰ってきました。本部役員を決める手紙には「やりたい やっても良い 出来ない 理由」そして推薦したい人がいたら書く項目がありました。推薦をした人の名前は推薦者には教えないと書いてあったのですが、これって人間関係が悪くなる元だとは思いませんか? 知らない誰かに推薦されたら気持ち悪いですよね。私はこの用紙は未提出にする予定です。
推薦者を書くつもりはありませんが、この用紙を普通に提出したらこのやり方を認めたことになるような気がしたからです。とにかく関わりたくない組織だと思っています。
川端さん不幸な人ですね⤵⤵
もっと学校巻き込まないと、、、Pだけでは、無理!学校も、地域も味方にしないとね
PTA改革も働き方改革も皆んな勘違いしてませんか?本当の改革とは皆んなが楽しいと思うPTA、職場の環境作りだと思います。私は7年間、会長、副会長を務めていますが、さほど負担に感じた事はありませんが、負担と感じるのは具体的に何処ですか?
子供の為なら親として最善を尽くすのは当たり前の事じゃないですか?PTA活動なんて長い人生の中のわずかな時間じゃないですか、親としてもう少し心の余裕を持つ事が大事だと思います。
PTA役員が全員就労していて平日の活動、まして夜なんて、とても無理なので、役員会を土曜日にしてほしいと学校に要望をだしたら、「教員も働き方改革で、土曜日は無理です」と、伝えられた。私たちも平日も働いてるけど?そのために休日をしだしてるのに?学校行事参加で、有給ギリギリ、パートタイマーの人は収入は減るはで、生活と子育てに支障がでてるのにPTAのこの逃げ場のなさが何十年と続いた理由。根本的にお母さんたちは子供のために自己犠牲を厭わないものだというのをみんなうっすらわかっていてのこの制度なのだとしか思えない。私たちの子供の価値観、このまま大人になったら、やはり同じ価値観のこどもしか育たない。
PTAのない学校はありますよ。その代わり、実に先生たちがしっかり学校行事を教員と生徒たちで運営しています。未加入の子供が差別される?子供のためのPTAなのに何千円払わないからサービス受ける資格ないなんて、つまらないこといわないで大きな心で見守るのがPTAのparentの使命だとおもうんだけどな。
うちの地域は、いまだに入学と同時に自動(強制)加入です。個人情報保護法も守られておらず、学校からPTAに児童名簿が当然のように流用されていて驚きました。本来、任意加入であることを知らない保護者も多いです。(現会長は熊本裁判を知らなかった)
一番理解し難いのは、単Pから市P、県Pという上部組織への上納金。多額のお金を使って開催される研究会。「子供のため」と口では綺麗ごとを言いながら、やってることは政治です。本当に子供のためなら、親の(特に母親)負担は軽くすべきなのに。子供の下校時間にかぶる講演会なんてやるべきではない。休日に、自分の夫や子供は家に置いて、顔も名前も知らない他所のパパやママがやってるソフトボールやバレーボールの試合の応援に強制参加させられることのどこが「子供のため」なのか?
深く関われば関わるほど、疑問と矛盾ばかりが目につきます。今、本部執行部で役職についていますが、任期を終えたら退会を申し出て「PTAはやめられるんだよ」を見せる我が校の第1号になろうと思っています。