「保育士を見捨てないで」の声を届けたい コロナ禍で浮き彫り、保育現場の窮状を変えるために
「あした退職する予定でしたが、記事を見てもう少し頑張ろうと」
待機児童問題や保育士不足、保育の質…。東京すくすくで手厚く取り上げているテーマの一つが、子どもが育つ環境や保育現場で働く人たちの状況を伝える記事です。新型コロナウイルスの感染が広がる今は、毎日のように保育士らから切実な声が届いています。
国は、待機児童対策を重点施策に位置付けますが、少ない保育士が多くの子を預かる状況や長時間労働、低賃金などの課題があり、より良い保育環境をつくる取り組みは不十分です。コロナ禍でこうした状況への怒りや不満が噴き出しているようにも見えます。
「あした退職する予定でしたが、記事を見てもう少し頑張ろうと思いました」。大型連休明け、大阪府の保育士の女性から編集チームにメールが届きました。コロナ対応で疲弊する保育現場からのコメントを紹介した記事を見たそうです。
誤解を招く政府のCMにショック「通勤中に罵声を浴びせられた」
政府は先月、医療従事者の子どもの預かりを拒否する保育所があるとして、こうした対応をしないよう求めるテレビCMを放映しました。女性は、全ての保育施設が同様の対応をしていると誤解され、通勤中に知らない人から罵声を浴びせられたそうです。心身が不調になり、仕事を辞めることも考えました。
勤務する保育所で着替えるため、ジャージーを5枚用意。1日に10枚使うマスクは、ミシンを買い20枚手作りしたそうです。「つらい思いをしている保育士はたくさんいる。私たちを見捨てないで」と訴えます。国のCMに対しては、他にも怒りの声が寄せられました。
マスクも消毒液も足りない…3密を覚悟で出勤 コメント300件
マスクや消毒液が足りない中、「3密」になりやすい職場に出勤せざるを得ない保育士ら。「園内を消毒して、残業も増えている」「政府にはもっと利用者の制限、時間短縮、マスクの支給、保育士の給料の値上げ、補償をお願いしたい」という訴えもあります。この2カ月で、保育現場の窮状を訴えるコメントは300件ほど届いています。
一方、保育士たちは、休園や登園を控えている家庭で過ごす子どもたちの様子を気に掛けています。
東京都内の認可保育所園長で、NPO法人こども発達実践協議会代表理事の河合清美さん(47)は「『マスクして!』『あちこち触らない』と怒られることが増えているのではないかと心配」と子どもたちを気遣います。協議会では、ウイルスの知識を分かりやすく伝える紙芝居を作り、読み聞かせ動画を公開しています。
保育所は、子どもたちの成長や発達、子育て支援に欠かせない場所です。現場からの声を改善につなげられるよう、これからも東京すくすくでも、東京新聞の紙面でも伝えていきます。
なるほど!
グッときた
もやもや...
もっと
知りたい






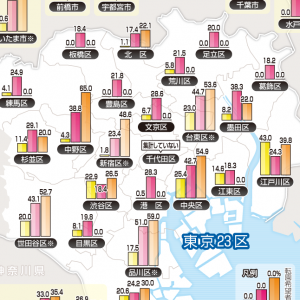





保育士です。
育休・産休中の人も普通に預け、両親共に在宅の方も長時間預ける現状。私たちの負担はどんどん大きくなります。いっそ、保育園が休園すれば、それを理由に仕事を自粛せざるを得なくなり、コロナ感染者も減るのではないでしょうか。
一緒に給食を食べることも禁止され、別部屋で5分以内に食べろと園長から言われました。私たちだけ、何でそんなに負担しなければならないのでしょうか。
医療従事者の方が大変なのは充分承知していますが、保育士は何の補償も援助もないまま、危険にさらされています。都内に勤務されている保護者の方も沢山いるので。
私たち保育士は、どれだけ苦しめばわかってもらえるのでしょうか。
保育士です。コロナ禍の中、保育士はまるでこの世にいないかのような扱いをされているようです。世の中の歪みや矛盾を一身に背負わされ続けています。在宅勤務の保護者に家庭保育の協力依頼をすれば逆ギレされ、開園していれば開園してるから預けなきゃならなくなると逆ギレされます。保護者が本気で子どもの命を守ろうとしなければ、社会は動かないです。保育園は身代わり不動尊ではありません。ガス抜きに使っても何も改善されません。ただただ子どもの命が危険にさらされ続けます。保護がこどもを守るために自分の身を切らなければならない時だと思います。いつも通りにはいかないのが非常事態なんです。非常事態は終わったことになりましたが、この状態ではだらだら続くように思います。
都内認可園ですが、緊急事態宣言中も開園し続け、医療従事者やひとり親家庭に限らず、希望される方は全員保育を行って来ました。平均して登園は全体の3分の1から4分の1程度でしたが、保育の現場で密を避けることは出来ません。国は自治体に、自治体は各園に、園を持つ事業者は現場に丸投げで、物資も届かず、子どもが少ない日は有休消化または有休の前借りで早退することを迫られました。表向き感染者は出ていませんが、この間体調不良で苦しんだ職員も居ました。
来週から、100人以上の定員の多くが登園します。小学校以上は再開に当たり分散登校、マスク着用、机の間隔、様々な対策が講じられるようですが、保育園の実態はないことにされていると感じます。現在の施設設置の最低基準に沿った保育室の広さ、定員では、昼寝の布団の間隔をあけることも、向き合わないで食事をすることも出来ません。勿論3〜4歳より小さい子はマスクも出来ません。マスクは寧ろ危険です。触れ合わないで保育はできませんから、密着は避けられません。厚労省も、自治体も、感染症対策を行った上で受け入れをと言っていますが、掛け声だけで現場を見ることも物資が届くこともありません。
今すぐどうにかなることではないですが、せめて保育の現場が見えないかの様な議論から、現実に目を向けた議論にシフトして頂きたいです。
保育園の看護師です。
私の自治体は、23区外ですが、それなりの感染者もいますし、働いて見える保護者の方もたいてい対人関係の仕事。あちこちが危険と隣り合わせですね。それぞれのフィールドで頑張っている。もちろん、保育士さんも同じです。
保育現場の不満の一番の原因は、厚生省からの『新型コロナウイルスによる保育現場の生活の工夫・遊びの制限』が明確にされていないことなのではないかと思います。
施設内の消毒や感染症対策は、コロナよりもはるかに前から対策済みです。問題なのは、なるべく三密を避けて過ごすなかでの見えないウイルスとの戦いで、開園指示はあるのに具体的な対策が遊び・集団生活として厚生省から未だに通知がないことなのです。保育のなかで何かをするために避けられない三密を回避しつつ、どこまで出来るか?毎日のように悩み苦しんでいます。
実際に厚生労働省に問い合わせしましたが、緊急事態宣言を出すことで登園児数がかなり減ると見込んでいたようで、実際の状況をお伝えしたところ、驚かれていました。そして、『散歩をするなら、三密を避けるために大人1人に対して園児5~6人・・・できれば、それより少な目で』とも言われましたし、散歩するより園庭で室内で過ごしてくださいと言われました。
夏に向けたプールは自治体が『学校もやらないから』と中止するよう言われました。この指示がある前に三密を避けた対策を検討し、実施することを考えていたので、職員は落胆していました。保健所は『保育現場で三密を避けることは難しい現状。学校のように休園になることが子どもにとっては安全ですね。でも、なりませんよね。』とのこと。夏に向け、せめて水遊びとも考えていましたが、特に1~3歳児あたりがヨダレやらオムツやらマスクの着用も含め困難なことが多く、人手不足も重なり、厳しい現実。水遊びと言っても幅があり、やって良いものとダメなものの線引きも難しい。現場は細かな配慮が必要で、本当に悩んでいるのにも関わらず、厚生省の方針は何度調べても見当たらず、指示もなく、自治体に問い合わせても『検討します、調べます』とだけで、返事が来ない。
子どもたちが『保育園に来ても、何にもできないね』と言います。保育士さんは、遊びも季節感を取り入れ、さまざまな工夫をして楽しませる時間を提供しています。苦しみながら。
働く保護者への労いも忘れていませんよ。定期的にご家庭へ連絡も入れて、ご家庭で過ごしている保護者が子育てや家事に疲れたら、お預かりもしているのです。保育士さんは、お預かりする子どもとご家族のことを大切に思っています。
だから、保護者と離れて過ごす時間を子どもが寂しくなく、楽しく健康的に過ごせるように、ずっと働いています。身体的、精神的、社会的にフォローもしつつ、個別的に出来る対応も、本当に空き時間があれば話し合っているのです。
だから、悩むことが多いからこそ、自治体や保健所や管轄の厚生省が今後の活動に向けて、改めて最低限の示していただきたい。
学校のこともいえますが、大人が大変だから~でなく、子どものためと思うなら、子どもが苦しまない伸び伸びとできる内容を最大限、大人が合わせていきたいです。
保育士さんって、そういう面では、本当にプロとして尊敬しますよ。彼ら・彼女らの仕事に対する姿勢は立派ですよ。指示を出される前に現場にも出向いて、現状を把握してもらえたら、ありがたいですね。
長々とすいません。
自治体の方針に怒っているのですね?
自治体の対応や、認可保育園によっては保育園の対応はまちまちです。自分の周りで起きている事だけが、保育園の事実ではありません。
せめて、23区の対応を見てみるといいと思います。認可保育園の対応は、もっと多様です。
「事実」私が働いている職場では、休園もしていませんし、医療従事者のみの保育でもありません。
緊急事態宣言禍で、「事実」をとらえることの大切さ感じます。世の中が混乱している時こそ、「客観的事実」って大切だと思いました。
今日の保育園では、緊急事態宣言解除で、登園人数が増えてきました。久しぶりに会ったこども同士が、ギューっと抱き合ったり、じゃれあっています。ままごと遊びも、虫探しもみーんな、くっついています。密密です。
うちの園はすべての業種を受け入れています。
まあまあ、、、一部の地域の状況なのかもしれないけど、発症率や死亡率たかかったら本当に危ないですよね保育園も。三密暮らしですもん。
コロナ対応の生活で何かイライラされてることが、でちゃってるみたいですね。
保育園の現状を聞きたいです。もうスルーして、皆さんが工夫していることや困っていること、教えてほしいです。
ご本人達がどう捉えているかは知りませんが、客観的な事実として、保育園は現在休園か、両父母医療従事者の子供しか預かってませんよね?エッセンシャルワーカーとしては機能していない現状をまず認めましょうよ。
しかも医療従事者の子供を預かりを拒否したり、子供を隔離したりしている現実もありますよね?
仰っていることと、保育園の現実とがあまりに解離しています。口先の理想論の前に仕事を責任持ってやりましょう。
不平不満に聞こえますか?
休みたいから言っているのではありません。働く人たちの生活を守るために、発言しているのです。
現に、医療関係者の方々、社会インフラを支える人々、在宅で仕事をしている人々のこどもたちを預かっています。不安を抱えながらも、こどもや、保護者の前では、笑顔で、今何ができるのかを精一杯考えて日々を過ごしています。
鼻水と涙とヨダレのこどもたちを抱き上げ、笑顔にして、保護者を仕事に送り出しているのです。
保護者の安心とは、なんでしょうか?こどもたちが、健康にすくすくと育つことではないですか?
こどもの発達と保護者の就労を支えるのが保育の仕事です。そこを守れるのかの話をしているのです。
命を守り育てる現場の人間として、私も声をあげていきます。
誤解があるのかしら?25日 10:40に投稿のかたは 何のために ここに来たのですか?
保育士も社会を回すための仕事をしていますよ。大勢の『子ども達』にクラスターがおきないように気を付けていくことに神経を使っています。私達が日々接しているのは命ですから、今までだって神経を使っていました。
「医師や看護師、介護士、スーパーや薬局、物流やメーカー、ライフライン、役所や警察、救急隊員。ここに上げ切れないほど多くの人がみんな感染リスクが高い中で、自分たちの社会的意義、責任を全うするために必死に頑張っています。子どもを留守番させたり、預けたりしてまでも社会のために働いてくれているからこそ、普段の変わらない生活が出来ている」もちろんですとも! ここに保育士もはいります!
どの仕事も互いに支えたり支えられたりして成り立っているということには同意です。ここの保育士が言っているのは、職場の今の現場です。労働環境や雇用状況など 今現在の課題です。これは改善することで、子どもも保護者も子育て施設の職員も、社会にとってもプラスになることですから。
企業の経営者や法人、自治体の管理者は、いろいろ現状を話さず黙って言うこと聞く、自分に都合よい人材の方が良いに決まっていますよね? いったいあなたが何の人なのかはどうでもいいです。自分達は、物言う職員なので黙りませんよ。
保育を支えている保育士さん達の給与を含めた労働環境改善は早急にやらなければいけないと思います。
世界的な危機の中で、何故日本の保育士だけがこんなにも不平を述べているのか理解出来ない。
医師や看護師、介護士、スーパーや薬局、物流やメーカー、ライフライン、役所や警察、救急隊員。ここに上げ切れないほど多くの人がみんな感染リスクが高い中で、自分たちの社会的意義、責任を全うするために必死に頑張っています。
子どもを留守番させたり、預けたりしてまでも社会のために働いてくれているからこそ、普段の変わらない生活が出来ていることを保育士たちはどう考えているのでしょうか。
自分たちさえ休んで、普通に生活できればいいんですか?
今回の保育士たちの不平不満は、何故保育士の待遇が改善されないのか理解できることとなりました。利用者を批判し、責任を放棄するのを正当化できる程度の仕事なら、待遇が改善されないのも当然です。呆れました。
神奈川県内の認可保育園で働く者です。緊急事態宣言が、解除されてからの保育に不安を感じています。
宣言中は、こどもの出席人数が、2分の1から3分の1程でしたので、3密を取らない工夫ができましたが、解除後6月からの保育で、3密を取らないという事はどう考えても無理です。(換気は、できます。しています。)
福祉の貧困な日本の中で、環境しかり、体制しかり、どう工夫しろというのでしょうか。現場の保育者は、もしも自分が感染を広げてしまったらとビクビクしています。
報道で、フランスでは、集団の大きさを学校では15人、幼児は10人とすると聞きました。
私の職場では、幼児1クラス30人です。保護者も、今は「在宅勤務」の中で子育てを強いられています。解除されたら、秋冬になったら、どうなってしまうのでしょう。
工夫、工夫と言われても、そもそも狭い環境の中で、常に密を強いられている。その中でも工夫してこどもの成長を考えて保育をしている、保育者が沢山います。
基本的な、こどもの健康を守る事がこの様な日本の保育園の環境の中でできるのでしょうか。保護者を安心して仕事に送り出せるのでしょうか。
不安で、苦しくて仕方がありません。
公立保育士です。
この国は、次世代をになう大切な子どもを育てる気は無いのだと思う。時がたったら分かるのかもしれないが、本当に国を思ったり人を大切に思う人が居なくなり滅ぶのかもと、うっすらと感じてる。
子どもを丁寧にみれない人員配置数。子どもを見ること以外も何でも保育士がやらなくてはならず疲弊している。人を信用したり好きになることが出来ない園の子ども。諦めることばかり強要されているから。
子どもも大人も(保育士も)幸せに日々を過ごせる方法があるのに。何を幸せと思うかの違いなのかな?
自分が仕事をしている自治体が大事にしているのは、管理者が不機嫌にならないようにする事だけのようです。
昔、まだ保育士を「保母」と呼んでいた頃に聞いた話があります。子どもには1票もないから、国は保育には何もしてくれないんだよ。と…。しかも保育士は声をあげないから好都合だと。だから令和のこの時代になってもこの有様、この扱いでしかないんだと痛感しています。
それでもこの仕事を辞められない理由は、やっぱり子どもは果てしなく可愛い。仕事の答え、成果がすぐに出なくても、自己満足にすぎませんがやり甲斐を感じさせてくれる。から…。
だったらこのままで構わないのでは!という無言の声が聞こえています。
宮城で非常勤で働いています。2歳児担任ですが、未満児は抱っこにおんぶや添い寝など、子供達が安心できるためには密接ならぬ密着しなくてはなりません。医療従事者やサービス業のお子さんを預かるために毎日出勤していました。しかし、看護師さんなんかと同じ国家資格もある保育士は手当てすら出ず非常勤なんかは手取り13万しかもらえません。基本給の最低賃金を全国統一値上げしてほしい。どうして医療従事者は給付金がもらえて、そのお子さんや様々な仕事に行かれる保護者やマスクもできない子供を保育する保育士にはなにも無いのか…。マスクの支給が始まったのもつい最近。それまでは自分で確保したマスクを使ってました。自粛期間中もコロナが出ていない地域は普通にみんな預けていきます。理解なんか得られない方も多い。特に親に変わって躾をしなくてはならない未満児。言葉も分からない子供を保育するのは保育士も仕事であれ大変です。事務時間も取れず、子供が起きたり泣いたりすれば休憩も返上。0歳児一対3人、1歳児一対6人も本来なら無理があります。月齢差も考えたら0歳児は一対2人、1歳児は一対3人くらいじゃないと、回りません。災害時なんか1歳児一対6人なんか助けられませんよ。保育士はメディアで取り上げられないことも多い仕事で、あまり大変さが伝わっていないのが現状。親は言いたいことや主張をし、クレームばかり。その対応も意にそぐわなければ、日々頑張って保育していても保育士否定に入ります。現にされました。
国は保育士不足解消にも、余裕ある保育ができるように待遇の改善をして下さい。保育士が足らなくなり、受け入れられないと、ますます子供を生んで働くことはできず少子化に拍車がかかるだけ。今の大人が高齢になった時に苦しむことにもつながりますね。保育士は楽しくもあり、やりがいのある仕事で誇りをもっています。だからこそ、保育士に対する考えを国をあげて変えていって欲しいです。